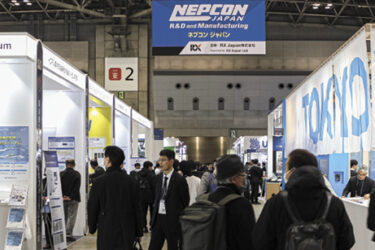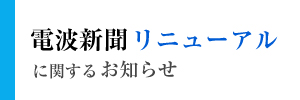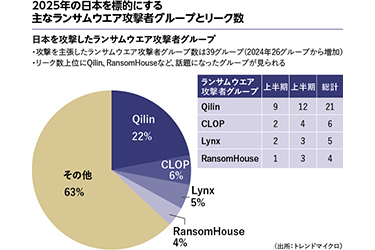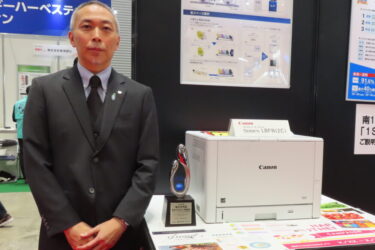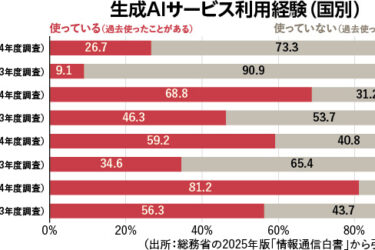2021.01.01 【音に魅せられて】Technics(パナソニック)〈3〉遊び心とDIGAの経験
パナソニックの高級オーディオブランド「Tecnics(テクニクス)」の歴史をアプライアンス社テクニクス事業推進室の井谷哲也CTO(最高技術責任者)/チーフエンジニアとともに振り返り、前回は井谷氏とテクニクスとの関わりについて聞いてきた。今回は2010年(平成22年)のテクニクスブランド終息と2014年(平成26年)の復活劇の裏側を見ていく。
(聞き手は電波新聞社メディア事業本部 水品唯)
■良い音への探求は不変
―2010年のブランド終息の際はどのような雰囲気だったのでしょうか。
井谷 2008年(平成20年)にダイレクト・ドライブ方式ターンテーブル「SL-1200MK6」の発売を最後に新製品の発売はなく、技術陣は複雑な思いでいましたね。特に2010年(平成22年)のブランド終息の際は、会社としてテクニクスの製品は出せないが技術開発はなくならないし、それよりも良い音を聴く環境づくりはブランドに関係なく必要だという思いもありました。
■変わらぬ技術追求

―ブランド終息後はHi-Fiオーディオの開発は凍結されたということだったのでしょうか?
井谷 音響の開発は、テクニクスだけではありません。もちろんパナソニックブランドでもオーディオは出していますし、AV機器の開発もあります。私自身は違う部門にいましたが、当時のオーディオのメンバーは、良い音を作るための開発は続けていました。
その一つのエピソードとして、若い時から顔見知りの技術メンバーが現在のテクニクス製品に搭載されているフルデジタルアンプ「JENOエンジン」の基となる技術を大学の研究室と一緒になって開発していました。中身は非常に面白いものでしたので、「一度きちんとやろう」という話になりました。そして作ったものを市場に届けようと。
■突破口はPMX5
―そのときは井谷さんも関わられたのでしょうか?
井谷 私自身はビデオビジネスユニット(BU)の先行開発メンバーの一人として独自のデジタルプラットフォーム「UniPhier(ユニフィエ)」の高画質領域とかHDMIなどを見ていましたが、2010年(平成22年)にビデオBUとオーディオBUが統合した時にオーディオの先行開発も見るようになったので、エンジニアが開発しているものを何とか形にしたいと思い、働きかけました。
そこで、その新しいフルデジタルアンプ技術を用いて開発したのがマイクロコンポ「SC-PMX5」です。2012年(平成24年)に、まずは欧州で発売しました。この製品、真剣に聴くととても良い音がするので、まずはキチンと聴いてもらい評価してもらおうということになり、DIGAの開発を通じて知り合った欧州のライターや評論家に聴いてもらいました。そうすると「この音はテクニクスではないか」と言われるほど高評価だったのです。それなら本格的にやってみようという話になったわけです。
翌年には日本でも本格的に動きだしてみようということで、ハイレゾリューション(ハイレゾ)音源対応になった次機種SC-PMX9を国内の評論家の方々に聴いてもらうことにしました。評価を聞きにいってみると、「電源ケーブルやスピーカケーブルを交換したら音が激変するよ」と言われるなど、意外と皆さん、いろいろといじって遊んでいたんですよ(笑)。そうした意見をもらいながら、今度は高級ケーブルを付属した「SC-PMX9LTD」を発売してみて、こちらも好評を得ました。こうした経緯もあり、もっと高みを目指そうという機運が高まってきたわけです。
■エンジニアの遊び心

―裏舞台ではいろいろなエピソードがありますね。
井谷 ちょうどデジタル化が進んでいる時期でもありましたからね。信号処理はしょせん半導体ですから、コストをかけなくても良い特性のものができるのですが、音質はそれだけでは決まりません。オーディオエンジニアとしては、より良い電源や部品を使って、もっと良い音を目指したいわけです。これも当時の話ですが、ある技術者がサウンドバー用のアンプ回路基板を小さなボックスに入れ、電源などを自作して、どこまで音が良くなるのかと、ひそかに遊んでいました。音を聴いてみると確かに良いので、それがきっかけとなってエンジニアたちがボランティアで「音符君」というデジタルアンプの試作機を作ったのです。開発予算は全くないので、経費で計上していた予算から捻出して皆で遊びだしました。こうした動きもテクニクス復活に向けての布石になっていきました。
■2013年本格始動

―実際のブランド復活の話は、いつぐらいから出てきたのでしょうか。
井谷 技術者らがそういった活動を経て徐々に自信をつけていたのが内部でも広まり、2013年(平成25年)ごろには、Hi-Fiオーディオシステムとして、後にテクニクス復活第1弾となる「R1シリーズ」や「C700シリーズ」の基になる話が出てきていました。ただ、テクニクスブランドを具体的に復活させるという話にはまだなっていなかったため、グレーで進んでいましたね。
ちょうどその頃にオーディオ事業はAVC社からアプライアンス社に変更になり、当時のカンパニー社長の高見和徳が私たちの取り組みに興味を持ってくれ、Goサインを出してくれました。そうした経緯から2013年8月に次世代Hi-Fiオーディオプロジェクトが立ち上がり、技術のプロジェクトリーダーを私がやることになりました。現在のテクニクス事業推進室長の小川理子は2014年(平成26年)に異動し、彼女のリーダーシップの下で本格的なテクニクスブランド復活の一歩を踏みだしたわけです。
■DIGAの経験が生きる
―お話を聞いていると、今のテクニクスの復活は井谷さんの経験があってこそという感じですね。

井谷 いろいろな意味で私自身は幸運だったのだと思います。テクニクスからDIGAという映像の世界に行き、そこで最先端の開発に携わることができましたし、事業自体も伸ばすことができました。その頃よく、「テクニクスのポリシーを受け継いでいるのはDIGAだ」と私は言っていました。実はオーディオは一体型や携帯型が主流になりシステム化され音質を磨くことなどが難しくなっていましたが、DIGAは昔のコンポーネントオーディオと同じいわゆる〝箱もの〟ですから、DIGAだけで完結しないのです。
どのテレビとつながるか分からないし、どのAVアンプとつながるかも分かりません。だからこそ何とつながっても最高のパフォーマンスを発揮するようにしないといけないわけです。逆に製品の階層を構築するのは比較的簡単です。チューナ数とHDD(ハードディスクドライブ)の容量で階層化できますので、最上位製品に高画質化技術など最高峰の技術を投入することでブランドをけん引し、下のラインに技術を展開するやり方です。まさしくHi-Fiコンポーネントの世界と同じだったのです。
そういうことをずっとやっていたため、復活の際に声がかかったのだと思っています。人にはガラパゴス諸島のゾウガメのように生き残っていたと言っています(笑)。逆にオーディオ部門に残っていたら環境変化に伴い部署異動などで生き残れてなかったかもしれないと感じています。(つづく)
次回は最終回です。テクニクス復活から現在までの音作りの考え方を聞きます。
【井谷哲也氏プロフィル】パナソニック アプライアンス社テクニクス事業推進室CTO(最高技術責任者)/チーフエンジニア
いたに・てつや 1958年1月20日生まれ。京都市出身。岡山大学工学部電気工学科卒。1980年、松下電器産業(現パナソニック)入社。81年、ステレオ事業部CDプレーヤ開発プロジェクト配属マイコン担当。82年、CDプレヤー1号機「SL-P10」発売。85年、ポータブルCDプレヤー1号機「SL-XP7」発売。86年、MLP(レーザーディスク)プロジェクト異動 映像信号処理担当。90年、世界初のデジタルTBC搭載「LX-1000」発売。95年、光ディスク事業部DVDプレーヤプロジェクト異動 映像信号処理担当。98年、世界初のプログレッシブDVDプレヤー「DVD-H1000」発売。2004年、HDMI搭載DVDプレヤー「DVD-S97」。05年、BDプレーヤプロジェクト異動 再生系映像信号処理担当/PHL Reference Chroma Processor/3Dプロジェクト。10年、ホームAVBU(NWBG)発足 オーディオ・ビデオ先行開発担当。13年、高級オーディオプロジェクト発足プロジェクトリーダー。14年、Technics復活。15年から現職。