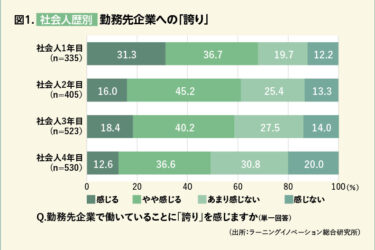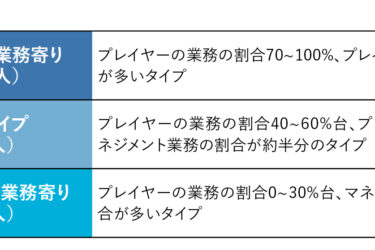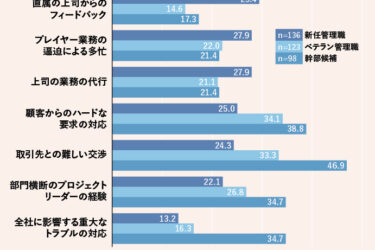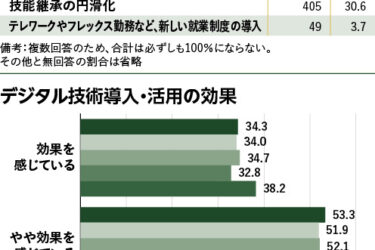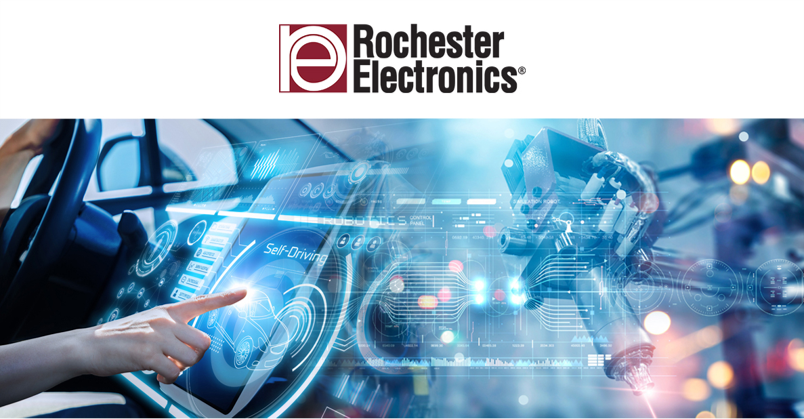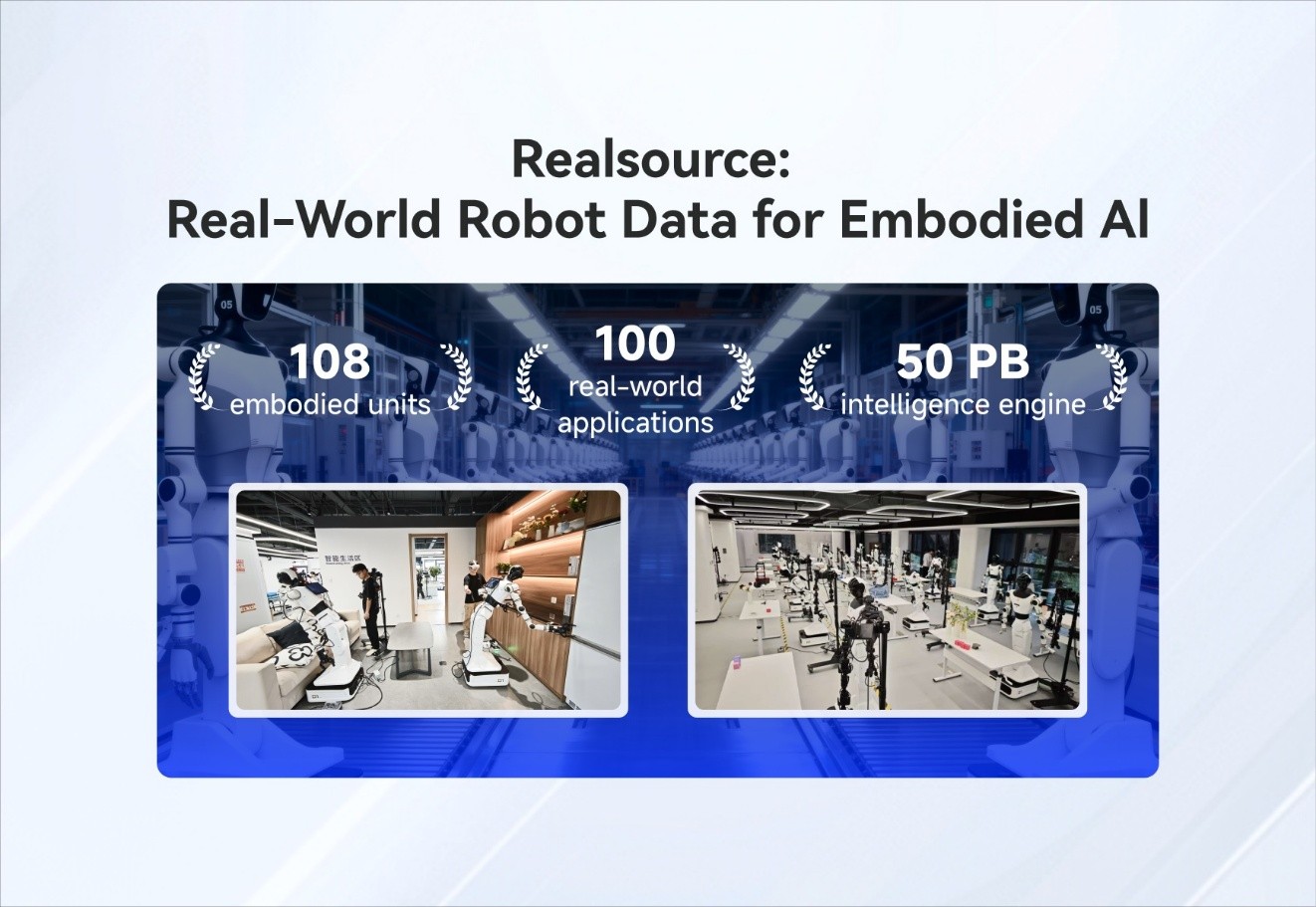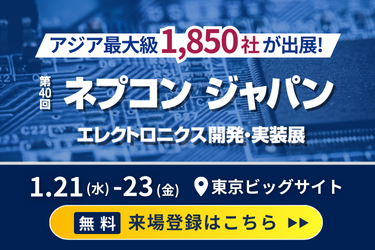2025.04.25 【育成のとびら】〈48〉管理職が人事評価・フィードバックを学び、何が変わったのか
本連載の44~47回で、人事評価は社員の「成長」に重要な起点の一つであり、評価、フィードバックする管理職の知識・スキルなどが重要であることを伝えてきた。
今回は、人事評価について管理職教育に取り組み、結果として全社の成長・学びの意欲を高めた建材メーカーの取り組み事例を紹介する。
この企業は、管理職によって評価やフィードバックの方法にばらつきが発生し、公平・公正な評価が担保できていないという課題を抱えていた。全社で社員教育に力を入れていきたいというトップの意向があったものの、各現場では業務の忙しさゆえ、研修受講などが思うように進まない状況でもあった。
そこで同社は評価のばらつきという課題に対して、管理職へ2段階で研修を設計した。まず、管理職全員が「人事評価フィードバック」や「部下の育成計画策定」をテーマとする研修を受講。人事考課に対する正しい知識をインプットし、認識の共通化を図った。
その上で、3回連続で実践型のスキル体得プログラムを実施。初回は、事前にインプットした人事考課の知識を踏まえて、実際の面談のフィードバックシーンを模したロールプレー学習に取り組んだ。
研修後は、そこでの学びを現場で実践することを徹底。2回目以降の研修では、現場で取り組んだ結果に対し、講師や同じ参加者からフィードバックをもらい、さらに次の実践につなげた。
こうした一連の教育の結果、現場ではより標準化された評価やフィードバックが行われ、管理職と部下の間の評価に対する納得感が以前より高まったという。
さらに、管理職の評価・フィードバックの変化は、部下の成長・学びに対しても、プラスの影響をもたらした。
管理職が面談などを通じ、部下一人一人の課題を具体的に把握した上で、さらなる成長に向けたフィードバックを行い学びを推奨することでポジティブな反応をする部下が増えたという。
例えば、以前は業務の忙しさから研修受講が後回しになっていた社員も、積極的に研修を受講するようになり、「受講してよかった」「役に立った」という反応が増えた。
学びの文化を醸成
管理職の人事評価教育への取り組みは、管理職の評価基準の統一化にとどまらず、フィードバック効果の高まりや、全社の教育・学びへの前向きな意識の醸成といった効果も生み出した。
実は、この取り組みが成功した背景には、経営トップが長期的な視点に立ち、教育の重要性を社員に伝え続けたことがある。
社長自ら、機会があるごとに社員に対し、「目先のことだけでなく、5年後、10年先、会社や自分がどう成長しているか、そのためには何が必要かを考えてほしい」というメッセージを発信し続けてきた。
こうした経営者のメッセージにより、管理職の評価やフィードバックが変化し、全社に教育と学びへの前向きな姿勢が広がったといえる。
次回からは、最新の調査から2025年度入社の新入社員が求める「理想の職場」「理想の社会人像」などを紹介する。
(つづく)
〈執筆構成=ALL DIFFERENT〉
【次回は5月第2週に掲載予定】