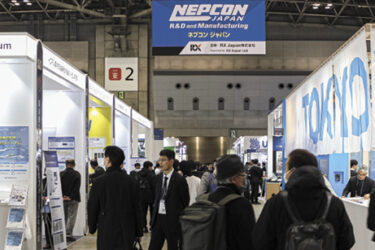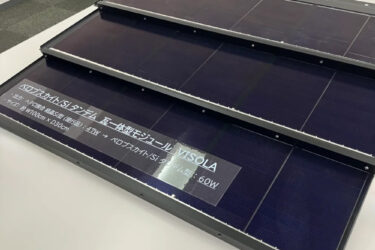2021.08.11 【この一冊】「清六の戦争 ある従軍記者の軌跡」(伊藤絵理子著、毎日新聞出版)
評者にとり、天に唾する面もある言葉だが、「八月ジャーナリズム」の表現が見聞きされるようになって久しい。戦争関連の報道が8月前後に集中しがちなメディアのあり方を評している。「大事な問題は時期を問わず報じるべきだ」との意見もあれば、「災害報道同様、節目に関心を喚起することも有意義」との意見もあり、功罪は相半ばしているともいえる。
戦前の新聞のあり方は、ジャーナリズムや学問の世界でもかねて検証されている。この本は、70年代生まれの現役記者が、縁者(自身の曽祖父の弟)が従軍記者だったと知り、その足取りをたどったもの。
表題の伊藤清六記者(1907~1945)は、岩手の貧しい農家に生まれた。だが向学心は強く、苦学のかいあって、宇都宮高等農林学校へ。新聞配達をしつつ学んだ。「僕はトルストイのように一生苦しんで最後に農村で死ぬのだろうと考えています。自分が自分の力で生きるという程尊いことはない」と語っていたそうだ。
卒業後、東京日日新聞(現・毎日新聞)の通信部記者や農政担当などを経て、日中戦争の従軍記者に。その仕事ぶりが一つの読みどころだ。
さらに、戦争末期に近いころ、フィリピンに派遣される。その前後のくだりも、大きな読みどころだ。大阪毎日新聞社が設立した「マニラ新聞」に携わった後、米軍の攻撃から逃れる形で日本軍と共に山中の洞窟へ。戦況などを伝えるため、陣中新聞を発行した。部数350、ガリ版・わら半紙ながら、兵士の投稿なども載せ、おそらくむさぼるように読まれていたと思われる。厚労省の記録では、38歳で戦病死、実際は餓死だった。
著者にとり、身内の足跡の追体験だけに、重い作業だったと想像される労作。昨夏の新聞連載当時、評者も読んでいた。国の圧力に屈したメディア、といった単純な構図でもないことの一端がうかがわれる。個人の思いと組織の論理のあり方も考えさせられる。
有名な俳句「八月や六日九日十五日」(初出については諸説)で詠まれるこの季節。歴史の風化を防ぎ、今と将来を考えるため、こうした関連書などをもとに思いを巡らせることの意義は多くの人が感じるだろう。過去に目を閉ざす者は現在にも盲目となる、と言われるだけに。
毎日新聞出版。190ページ。1650円(税込み)。