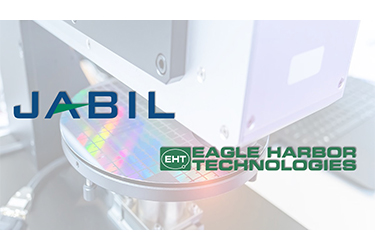2025.05.09 「震災を嫌な歴史で終わらせない」 ダイヤモンド半導体を原発廃炉に 福島県に世界初の量産工場
大熊ダイヤモンドデバイスのダイヤモンド半導体
人工ダイヤモンドを材料とする「ダイヤモンド半導体」を世界で初めて量産する工場の建設に向けた動きが、福島県で始まっている。整備するのは、北隣の双葉町にまたがって東京電力福島第一原子力発電所がある大熊町。原発の廃炉作業に活用する半導体を製造する。北海道大学と産業技術総合研究所(産総研)発のスタートアップ、大熊ダイヤモンドデバイス(札幌市北区)の挑戦が本格化している。
... (つづく)