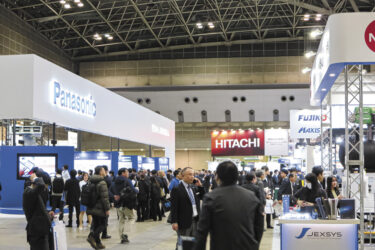2025.01.30 【新春インタビュー】日本事務器 田中啓一社長
お客さまに寄り添い100年迎える
ITトータルソリューション&サービスを提供する日本事務器が昨年2月に創業100周年を迎えた。昨年12月にはパレスホテル東京(東京都千代田区)で取引先向け感謝会を開催し、電波新聞社のほか、首都圏近郊で取引のある企業や業界団体の関係者ら約350人が出席し、節目を祝った。田中啓一社長に1世紀にわたる企業活動の歩みと今後の事業戦略を聞いた。
―創業100年という大きな節目の年になった2024年はどんな年でしたか。
感謝の意を表す活動
田中 われわれが100年間事業を続けてこられたのはステークホルダーのみなさんのおかげであり、この1年をかけて感謝の意を表す活動をしてきた。お客さまや、長年にわたり貢献してきてくれた社員・OBにも謝意を伝えたい。
全国41カ所に拠点を置き、ラストワンマイルのポジションでお客さまとのつながりを大切にしながら事業を展開してきた。また、100周年を迎えた中で、お客さまはもとより、社員が通う飲食店やビルの清掃業者などにもさまざまな形で感謝の意を伝えた。こうした取り組みを各地で開催することで、地域に支えられてきたことを改めて実感した。
100年は一通過点に過ぎないが、結果として多くのステークホルダーに触れる機会が増えたことがうれしかったことの一つだ。
―100年生き残るためにどう事業内容を変化させ、時代に適応してきましたか。
お客さまの経営の後押し
田中 変わらないところと変わってきたところ両方ある。BtoB企業であることは変わらず、お客さまの事業経営をより良い方向に後押しすることがスタートラインだ。最初はキャビネットやタイプライターを輸入し提供してきたが、われわれがプロダクトを開発する取り組みも進めるようになった。
IT企業は東京・大阪・名古屋に拠点を構えることが多いが、当社は全国に拠点を設け、お客さまのすぐ近くでサポートできる体制を整えてきた。また、より充実したサポートのために社内の体制として、地域を超えた連携ができるように組織も変化してきている。例えば、ハッシュタグ型組織で部署や地域関係なく自然発生的にプロジェクトチームが生まれて事業に取り組むといったことも当社の特徴だ。
お客さまの日々の業務をよく知り、かつ提供するものにも精通していることの強みはいつの時代でも変わらない。どの時代でもお客さまの一番近くで寄り添ってきた。
生成AI(人工知能)など先端技術には詳しくても、エンドユーザーの事業をよく知らなければ最適なシステムは提供できない。
サービスを導入して終わりではなく、使いこなし、さらに次の施策を提案する「お節介度合い」が高いのが当社の強みだ。
―生成AIなど新しい技術への取り組みは。
田中 生成AIもどう使えばいいのか確立していない面も多く、まだ具体的にサービスとして提案する段階ではないが、お客さまと一緒に試してみるという姿勢で取り組んでいる。また、当社の中でも三つの分野でAIの活用シーンを広げる取り組みを進めている。
一つ目は、社内の製品やお客さま向けサービスに生成AIを組み込むことによって競争力を上げることだ。製品自体だけでなく、例えば、1500㌻ある健診システムのマニュアルをAIに聞けば答えてくれるなどの付加価値も合わせることでさらにサービスの質を向上させていきたい。
二つ目は、AIを社員の相棒にすることで日々の業務のパフォーマンスを向上させる取り組みを研究している。
三つ目は、お客さまがAIを使って新規事業に取り組みたい時にお手伝いができるという支援だ。
パートナーや取引先各社が財産

―注力している分野や製品は。
異なるUIに着目
田中 病院の電子カルテでも、製造業の生産管理システムでも、これまではユーザーインターフェース(UI)はパソコンが当たり前だったが、スマートフォンが当たり前になり、さらにウエアラブルデバイスやスマートグラスになるとも言われている。異なるUIでの使い方が目をつけるべきポイントだと考えている。
例えば、スマートグラスを装着した現場の新人エンジニアと同じ画面を熟練社員が共有して指示を出したりとさまざまな応用ができる。
―攻めていく事業領域は。
三つに分けて事業展開
田中 当社は既存領域、成長領域、創造領域の三つに分けて事業展開している。既存領域は民需やヘルスケア、文教・公共などのわれわれが今まで取り組んできた分野である。当社はこれまでの経験や実績から、お客さまと深いコミュニケーションが取れるというところに強みがあるので、その強みを生かしさらに活動を広げていきたい。
成長領域は、既存領域の周辺の成長が見込める分野のことである。お客さまの事業経営のIT化だけでなく、その周りで必要なさまざまなことに目を向け、新しいサービス機能の拡充に取り組みを進めており、そこには、デジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みも加わってくる。
創造領域は、今まで取り組んでいなかった事業分野である。社内ベンチャーのようなプロジェクトを発足するなど取り組みが進んでいる。チャレンジの領域であるため、いろいろと試してみることを重視している。
―101年目に当たる2025年の市場動向は。
田中 為替や米大統領就任の影響など不透明な部分もあるが、DXの需要はこの先も続くとみている。それをわれわれ一社だけで解決するのは難しく、パートナー連携は一層重要になる。ソフトウェア協会(SAJ)や日本コンピュータシステム販売店協会(JCSSA)の会員企業と横のつながりを大切にしていきたい。
生成AIも必須だ。生成AIのない世界で何かしようというのはもう無理だと思っている。生成AIと人間とロボットが当たり前のように共存する時代が始まると思う。
いつでも変われる企業体質に
―次の100年に向けたビジョンや将来像は。
田中 お客さまに対して価値ある企業、必要である企業であり続けなければならない。そのための模索と、必要な力を蓄えるために一番変わらなければいけない時期にこれから入る。延長線上で伸ばせばいいという考えでは立ちいかなくなる。
社内キャッチフレーズである「Change to Change」はいつでも変われる体質に変わろうという意味。1回変われば終わりではなく、必要ならいつでも変化する。ただ、こだわりは持つが固執はしないでいたい。
100年の歩みをひもとけば、戦争もあったし事業の危機もあった。乗り越えてこられたのはチームワークの力だ。チームワークが存続できてきたからこそ、底力が常にチームで発揮できたと感じている。
アーティストは、自己表現であり自分が作ったものがどう受け取ってもらえるか相手次第。デザイナーは、相手がどう受け取るかを狙って何か作る。われわれはデザイナーのスタイルでいきたい。受け取る側の気持ち、利用者視点で物事を捉えていくことをわれわれの価値の指針にしていきたい。
(聞き手は電波新聞社 代表取締役社長 平山勉)
日本事務器 100年の歩み
1924年 関東大震災の5カ月後、日本事務器商会として東京・日本橋で創業
計算機、タイプライター、タイムレコーダー、複写機などを扱う
1929年 国産初のビジブルレコーダバイデキス開発・発売
1948年 株式会社に改組
1961年 NECと提携、国産初の「NEAC」超小型電子計算機取り扱い決定
1981年 NEC日本語ワードプロセッサー「文豪」発売
1983年 NECパーソナルコンピューター「PC-9800」発売
1991年 通商産業省SI認定企業となる
1999年 統合ヘルプデスクセンター開設
2008年 本社を現在地(東京都渋谷区)に移転
2015年 海外準備室を設置
2018年 シンガポール駐在員事務所を現地法人化
2024年 創業100周年