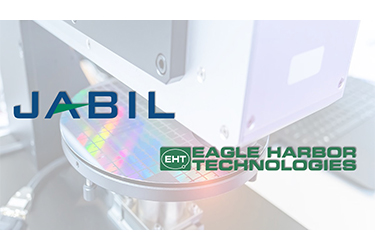2025.07.18 AIで進化するコンタクトセンター モビルス提供ツールの導入事例に迫る
クオリカでDXを推進する伊藤氏(左)と、モビルスの技術担当者長谷部氏
人工知能(AI)を活用してコンタクトセンターの応対品質と業務効率を高める――。企業の顧客対応を支援するモビルスが、そんな取り組みで存在感を放っている。顧客との接点はどこまで進化したのか。AIでオペレーターの回答をサポートする同社の「MooA CommNavi(ムーアコミュナビ)」の導入事例に迫った。
◇ ◇
ムーアコミュナビは、顧客と電話でやり取りする際にリアルタイムで音声認識し文字起こしを行うツールで、生成AIが通話内容の意図を抽... (つづく)