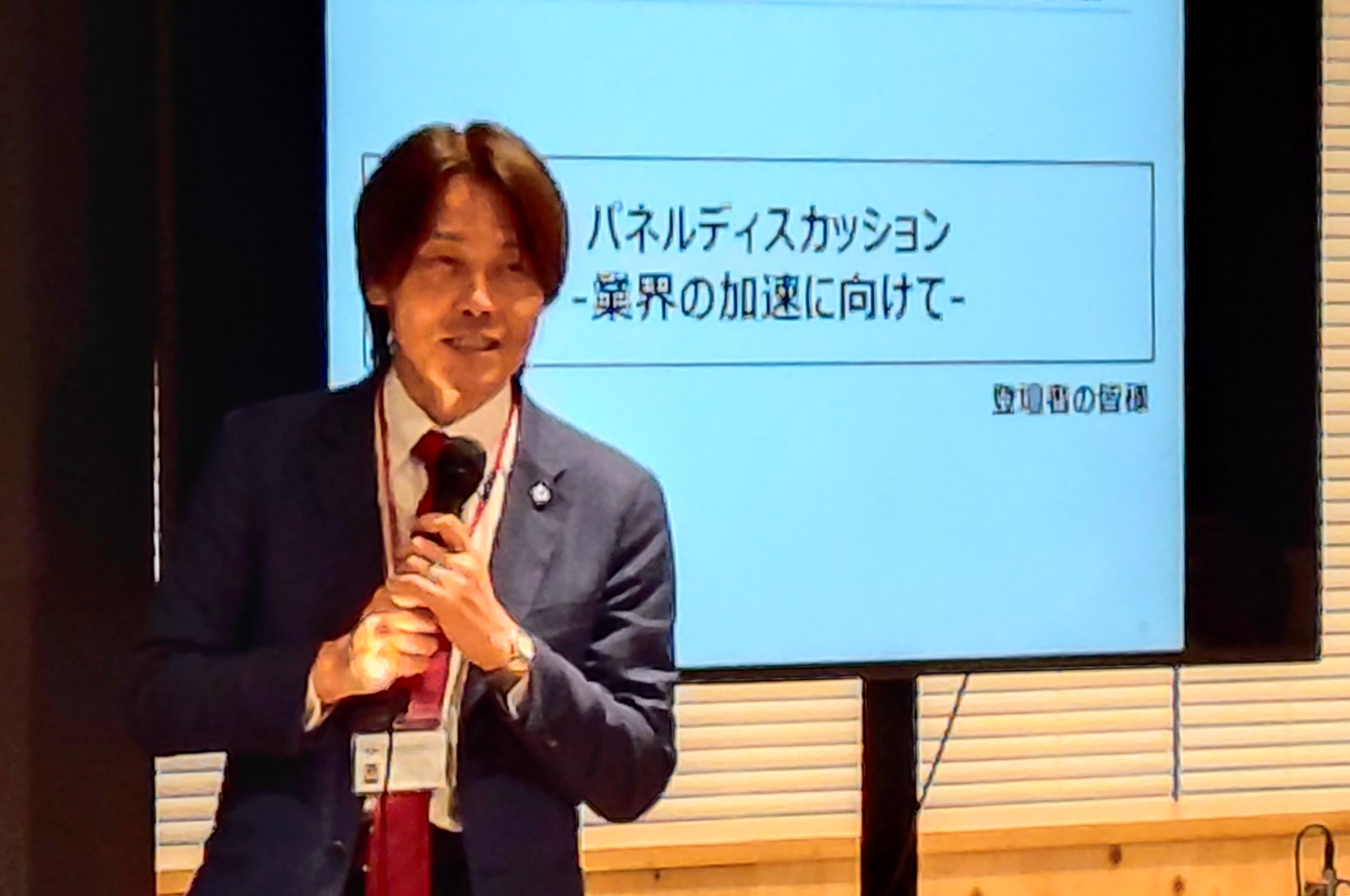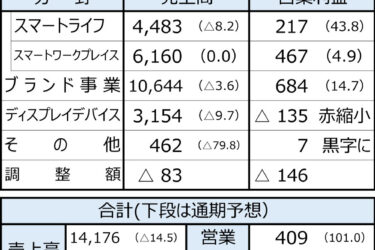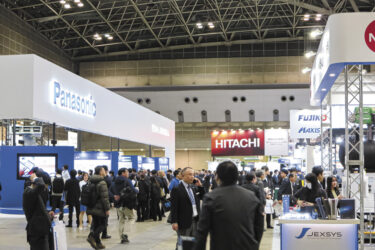2025.10.21 万博で好評 急げ!培養肉の産業化 培養肉コンソーシアムが報告会
多くの出席者が集まった第1回報告総会
培養肉の普及・促進を図る「培養肉未来創造コンソーシアム」の第1回報告総会が17日、大阪市北区の中之島クロスで開催された。約80人が出席した。
主催は、大阪大学と島津製作所、伊藤ハム米久ホールディングス、TOPPANホールディングス、シグマクシス、ZACROSが運営する普及団体「培養肉未来創造コンソーシアム」。
培養肉は、牛や豚などから細胞を採取、増殖させて組織を形成する。基本的に食肉の細胞のみでつくられるため、大豆などの成分を肉のように加工する代替肉とは根本的に異なる。このほど閉幕した大阪・関西万博の大阪ヘルスケア・パビリオンで培養肉が展示され、多くの来場者の関心を集めた。
万博での関心の高さを受け、総会には多くのスタートアップや関係省庁が出席し、社会実装に向け取り組みの現状や今後の事業の進め方などについて報告。出席者は、熱心に聞き入っていた。
今後の動きについて農林水産省は、「フードテック推進ビジョンのもと、地方でのイベントを活発化させていく」(大臣官房新事業食品産業部新事業国際グループ村上真理子課長補佐)と説明。経済産業省は、「万博により培養肉の関心が高まった。社会実装に向け官民一体で地方を巻き込みながらの拠点形成が必要」(商務・サービスグループ生物化学産業課木田泰之課長補佐)との認識を示した。
培養肉の産業化に挑む企業からは、「ここ数年で培養肉に参入の企業が増えている。仲間づくりのためには細胞を提供してもよい」(オルガノイドファームの山木多恵子CEO)や「医薬品と食品の橋渡しをしたい」(ダイバースファームの島村雅晴共同創業者)といった考えが紹介。
コンソーシアムの代表を務める大阪大学大学院工学研究科の松﨑典弥教授は「各関係者とともに横展開して取り組んでいきたい」と、今後の方向性を示した。
島津製作所は分析機器メーカーの立場から、アミノ酸分析システムやガスクロマトグラフ質量分析計(GC‐MS)などを培養肉や代替肉の研究分野に提供している。