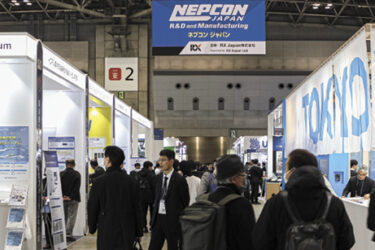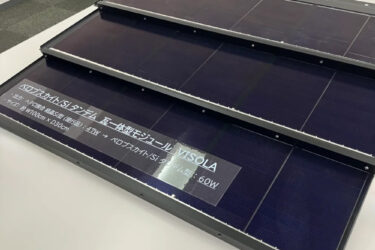2021.04.05 【この一冊】「推し、燃ゆ」宇佐見りん著 河出書房新社
SNSで日々コミュニケーションを交わす私たちは「スタンプみたいな屈託のない笑顔」や「絵文字みたいな、びっくり仰天、っていう表情」をしているのだろうか。
コロナ禍ではその記号のような面持ちさえマスクの下でうかがい知れなくなっているわけだが…。「単純化された感情を押し出しているうちに単純な人間になれそうな気がする」と物語の「あたし」は書く。
高校生の「あたし」が苦しいのは「肉の重さ」のためだ。「生まれたときから今までずっと、自分の肉が重たくてうっとうしかった」。「生きづらさ」は、「肉の重さ」に言い換えられる。
重さは、「月ごとに膜が剝がれ落ちる子宮」だったり、「首の後ろの冷え」だったり、「切っても抜いてもまた伸び続ける」足の爪や指の毛、「間抜けな音を立てて」こぼれ落ちる尿―などで体感・意識される。それら「勝手に与えられた動物としての役割」が不快な荷重として、毎日のしかかってくる。
ピーターパンは重さから自由な存在だ。「あたし」はその「永遠の少年」を子役時代に演じたアイドルを「推す」時だけ「重さから逃れられる」といい、すがるようにその偶像を追いかけるようになる。推しは生きがい、生活の中心、「背骨」になっていく。
勝手に誰かを好きになったり、応援したりすること。見返りを求めず、平等でも互恵的でもない。「バランスが崩れた一方的な関係性」にこそ「あたし」は救いを見いだす。
物語は「推しが燃えた。ファンを殴ったらしい」で始まる。なぜ重さにとらわれないはずの推しが、肉そのものの交渉に及んだのか。やがて「あたし」は、そんな推しにもある「肉の重さ」を知る―。
「アイドルが人になる」。重さから解放されることはない。ただその時、初めて「あたし」は重さを引きずりながら、はいつくばりつつ、生きていけそうな気がするのだった。
宙づりにされた少女のカバーイラストが印象的。著者は今年、本作で第164回芥川賞を21歳で受賞した。
河出書房新社。128ページ、1400円(税別)。