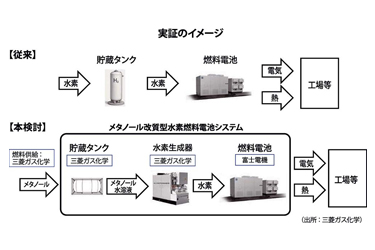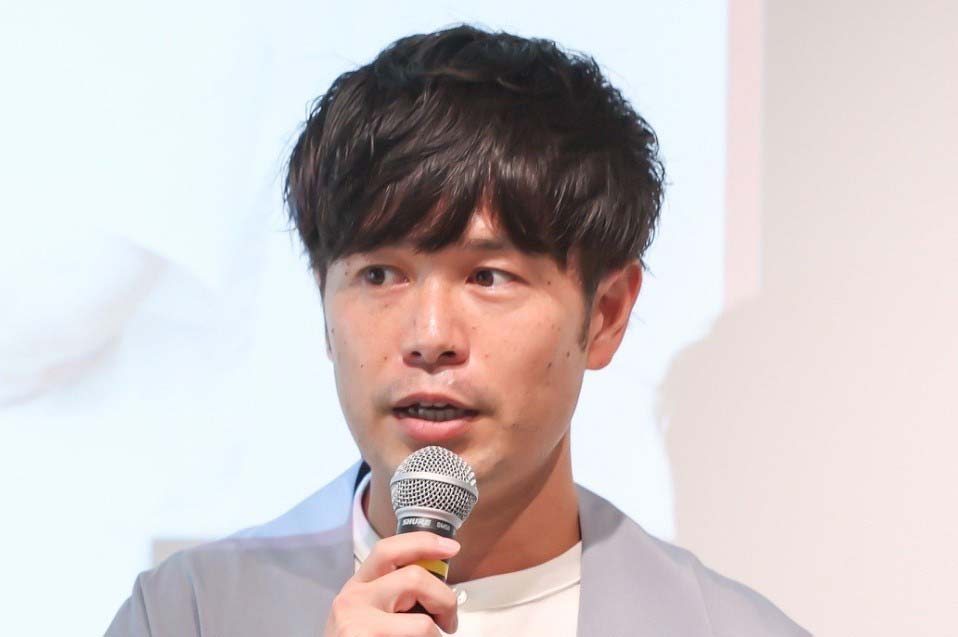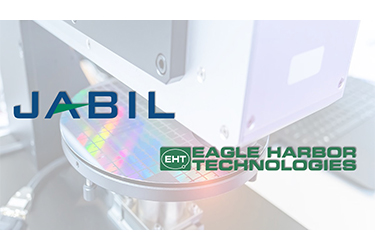2021.07.15 進む製造業の産官学連携大学の知見と企業の技術リソースを融合 新たな産業基盤構築
安川電機のオープンイノベーション拠点「安川テクノロジーセンタ」。九大とも連携する
製造業において産官学連携が進んでいる。大学の保有する知見を活用し、製造企業の技術リソースを組み合わせ、新たな産業基盤を構築する。産官学連携は新しい動きではないが、最近では連携の内容が製造技術にとどまらず、人材開発や高度な共同研究など多様化してきた。
安川電機はグループの技術開発を集約し、産官学連携によるオープンイノベーションを加速する狙いから、北九州市八幡西区の本社敷地内に研究開発拠点「安川テクノロジーセンタ(YTC)」を3月に開設した。同センターを活用し、研究開発や人材育成などを目指す一環として6月、九州大学との包括的連携に合意。これまで産業用ロボットの制御技術の開発などプロジェクトごとにテーマ設定してきた九州大学との関係をさらに強化し、共同研究に限らず、より広い範囲でのシナジー創出を目指す。
小笠原浩社長は「最先端の技術開発、異分野での連携、人材の育成など幅広い活動で共に持続的な成長と双方にとってプラスとなる関係を築き、グローバルな発展と地域貢献の実現に加え、お互いのビジョンの実現を目指す」と話す。
石橋達朗九州大学総長は「連携により、先端技術の発信や学生のインターンシップ、大学講座などのプログラムを通じて技術交流も視野に入れ、研究開発にとどまらない幅広いオープンイノベーションを加速させたい」と述べた。
農業用ドローン開発
ヤマハ発動機は産官学連携を積極的に推進。静岡大学との連携を強化し、新たに共同研究講座設置契約を結んだ。静岡大学が持つ総合的な知見を活用して早期課題解決、イノベーション創出を目指す。静岡大学は地域産業の発展や産業界のニーズを直接知ることで人材育成を推し進める。

スマート農業に向けた産業用ドローンの開発では、専門職大学として2019年度に創設された静岡県立農林環境専門職大学・農林大学校(静岡県磐田市)とも連携。産業用ドローン実技講習の支援などを通じて連携を深めている。また、静岡大学工学部・菊池将一准教授、東京電機大学・井尻政孝助教(当時/現東京都立大学システムデザイン学部助教)らの共同研究グループと、加熱することなくチタン合金表面に硬質な窒化層を短時間で形成させることに成功した。
学生支援債券に投資
FUJIは、日本学生支援機構が発行するソーシャルボンド(第62回日本学生支援債券)への投資を実施した。同機構は学生支援を先導する中核機関。日本の大学などで学ぶ学生に適切な修学の環境を整備し、次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的としている。
同社が投資を行った債券の発行による調達資金は、同機構が担う奨学金事業のうち、貸与奨学金の財源として活用される。
光産業創成大と連携
浜松ホトニクスは、光産業創成大学院大学(浜松市西区)の光技術を応用した新ビジネス創出に取り組む意欲的な人材の発掘に協力している。05年4月に開学した社会人を対象とする大学院大学で、光技術を応用した新産業創出を志す人材を育成するため、技術開発や事業開拓を目指す学生に光技術や経営に関する専門的知見を提供する。
光産業創成大学院大学、浜松ホトニクス、静岡大学、浜松医科大学は13年、光の最先端研究を目指し、世界の研究者との交流などを盛り込んだ「光の尖端都市HAMAMATSU」の実現に向けて共同宣言を行った。
その一環で、独創的な事業計画を表彰するビジネスコンテスト「Photonics Challenge(フォトニクスチャレンジ)2022」を開催する。最終審査会にはオブザーバーとして大手製造業や金融機関、投資会社の担当者を招いて将来の事業提携や支援につながる機会を提供するほか、コンテスト終了後も光産業創成大学院大学が中心となり継続的に事業計画の実現を支援する。