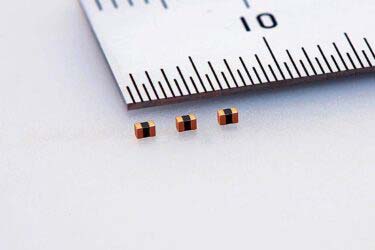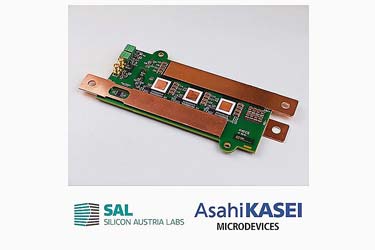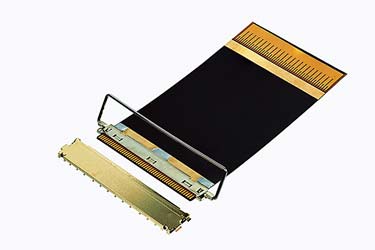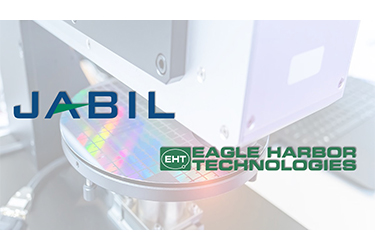2022.01.24 【新春インタビュー】タイコエレクトロニクスジャパン 松井啓社長
「ONE TE」で横の連携強く
―2021年を振り返るといかがでしたか。
松井 21年はたくさんの挑戦に直面しましたが、市場の回復にけん引された一年でした。半導体不足や、材料費の高騰、材料の供給不足の深刻化など市場全体で多くの課題に直面しましたが、われわれとしては生産ラインを止めずに稼働を続けていくことで、お客さまへの安定供給を実現しました。
特に材料の入手難に関しては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、タブレット端末などの巣ごもり関連製品の需要が増大したことも影響しました。
20年の年明け後に新型コロナの影響でいったん需要が落ちましたが、その後は急速な需要・生産回復になりました。大きく調整した後にV字回復した形になったため、オペレーションの面では大変厳しい状況でした。当社としては材料の入手難に対応するため、原材料メーカーとのコミュニケーションの強化や、エンドユーザーの協力をいただきながらデュアルソースを進めるなど、BCP強化に取り組みました。
―最近の業績動向は。
コロナ前を超える
松井 TE Connectivityグローバル全体の実績は、ポートフォリオの強さと多様性によって、19年のコロナ前のレベルを超える売り上げと収益を達成しました。
トランスポーテーションは、自動車生産台数が減少した中でも、電動化とコネクテッド化の市場拡大により高い成長を達成しています。インダストリアルも、FA(ファクトリーオートメーション)のアプリケーションへの設備投資需要の増加や、再生可能エネルギーアプリケーションの推進が成長をサポートしました。コミュニケーションズは、高速クラウドアプリケーションおよび生活家電の市場好調とコンテンツ成長にけん引され、高い伸びになりました。
これにより、21年度(21年9月期)通期の売上高は、報告ベースで前期比23%増の149億ドルとなりました。21年度は全セグメントが好調に推移し、特にEVやデータセンター、FAの長期的なトレンドから大きく恩恵を受けています。
―22年の市場をどのようにみておられますか。
松井 継続的なサプライチェーンの課題により市場は不安定なままですが、電動化、データとクラウド、FA、そして再生可能エネルギー向けの需要は引き続き拡大と考えています。
―22年の事業セグメント別の展望は。
松井 トランスポーテーションは、加速する電動化や、自動運転を支える高速通信化により、今後も自動車販売台数の伸びを上回る成長が期待できます。これらの先端分野に向けた提案活動を今後も進めていきます。
コミュニケーションズは、巣ごもり需要もありますし、今後も継続成長を期待しています。インダストリアルも需要の回復傾向が続くとみています。

―22年に向けた経営戦略は。
松井 今回の経験を踏まえて、デュアルソースの活用拡大や、供給のフレキシビリティー化に取り組みたいと考えています。マーケット動向を迅速に把握して、それに対応していくことを重視します。そして、回復力を維持し、コンテンツ成長に重点を置き、さらなる差別化を図ります。
今後も当社のフィロソフィーである「ONE TE」の精神に基づく経営を進めていきたいと考えています。
現在力を入れているのは、リモートワーク/スマートワークの活用を通じた働きやすい職場環境づくりです。そして、コミュニケーションの強化に取り組み、社員の声をできるだけ吸い上げられるようにしていきます。
これからの自動車産業は、自動車業界だけでモノづくりが完結するのではなく、ボーダーレス化が進んでいきます。われわれ自身も、「ONE TE」により、社内の横の連携を強くして、フレキシブルに対応していくというマインドで事業を展開していきたいと考えています。
当社では、スマートワークの導入に関しては、もともとコロナ前の時点からやり遂げたいと考えていました。リモートワークのプラス面、マイナス面は何かを把握し、理解した上で対応していきたいと思います。働き方改革で、従業員一人一人が自身の能力を最大限に発揮し、自発的に行動し、ほかの従業員と協働し、各所でイノベーションが起き、生き生きと働くことができる職場環境を提供する会社を目指したいと思います。
また、I&D(インクルージョンとダイバーシティ)を重視し、国籍やジェンダーなどに関係なく、斬新で革新的なアイデアが満ちあふれる、安全で多様性を受容する職場環境づくりに努めたいと思います。
30年に向けて持続可能性目標
―TEグローバルでは、M&A(企業の合併・買収)にも積極的に取り組まれています。
ポートフォリオ補完
松井 最近の事例では、TE Connectivityは21年にファクトリーオートメーションと、自動車向けの電子接続の分野をけん引するERNIグループAGを買収しました。買収の目的はTEの幅広いコネクティビティー関連製品のポートフォリオを補完するためであり、特にFA、自動車、医療、そのほか産業機器用向けの高速伝送用ファインピッチコネクターを強化するものになります。
同社の買収を通じて、基板接続におけるTEのエンジニアリングや製造拠点を強化し、顧客基盤とプレゼンス拡大を目指しています。今後は、お客さまが期待する、小型化、シグナルインテグリティー、データ速度や電力要件の向上、製品の信頼性に関するイノベーションを推進していくと思います。
―拠点体制拡充の取り組みは。
松井 21年には新たな国内営業拠点として「宇都宮営業所」を開設しました。宇都宮近郊の顧客に対し、敏速で細やかなサポートを提供してまいります。それ以外の既存拠点についても充実化を進めていきます。また、私が兼任で管轄するタイの「ゲートウエイ工場」とのコミュニケーションも強化します。今後も新しいプロジェクトが立ち上がっていきますので、ASEANの活性化に向け、タイの工場の拡張も検討していきます。
―ニューノーマル時代を考慮した経営戦略ではどんなことに取り組まれていますか。
DXとCXがテーマ
松井 DX(デジタルトランスフォーメーション、デジタル変革)とCX(カスタマーエクスペリエンス、顧客経験価値)を今年のテーマに掲げています。オンライン展示会などを活用したプロモーションを全世界で進めています。
自動車市場向けには、電動化や高速通信化に照準を合わせた製品開発と提案営業に努めています。当社は、コネクターやセンサーの「トータルソリューション プロバイダー」として、3年後、5年後を見据えた製品開発を進めています。デジタルツールを活用した情報発信を継続していきます。
―TEグローバルのサステナビリティーの取り組みは。
松井 TEはいつもサステナビリティーに配慮する事業活動を推進しています。20年8月にTEグローバルの「2030年に向けた新たな持続可能性目標」を設定し、将来的なビジョンにより重点を置いた長期的な持続可能性、および企業責任に関する戦略を発表しました。「温室効果ガス排出の35%削減」を含む九つのサステナビリティー目標の達成に向けて、初年度である21年度は着実な第一歩を踏み出せました。この一年間にTEは、温室ガスの排出量、エネルギー消費量および取水量の削減に取り組みました。
さらに、TEおよびTE Connectivity FoundationからSTEM助成金を提供することにより、65万人以上に影響を与え、次世代の持続可能なエンジニアの育成を支援します。これにより、30年までに300万人という目標に向けて好スタートを切りました。
掛川工場(静岡県掛川市)での省エネ化や廃材の削減などに取り組んでいますが、ここまで目標にミートする形で進捗(しんちょく)できています。
働き方改革で能力最大限発揮へ
―最近は物流面でも苦労されているのではないですか。
松井 サプライチェーンの課題にも直面し続けますが、当社はグローバル企業ですので、全世界に工場を持ち、顧客の近場でモノづくりが行えるということを評価していただいています。ただ、業界のサプライチェーン自体の組み替えなどが進む可能性もあるため、動向をしっかりと見極めながら対応していきたいと考えています。
―社長就任から1年が経過しましたが、手応えはいかがですか。
松井 「ONE TE」を志向した活動を進め、人と技術の多様化を推進した一年でした。スマートワークに関しては、当社はコロナ前から準備を進めてきました。事業所での試行や高い生産性を生み出す「新たな働き方」への変革を実現する社内トレーニングと本格導入説明会も開催し、21年の6月1日から本格展開になりました。働き方改革で、社員自身の能力を最大限に発揮させ、長く勤めたくなるような環境づくりに努めたいと思います。
また、社長としてのメッセージの発信を、全ての社員に十分伝えきれるように、22年に向けて、社員とのコミュニケーションの機会をさらに増やしていきたいと考えています。
(聞き手=電波新聞社 代表取締役社長 平山勉)