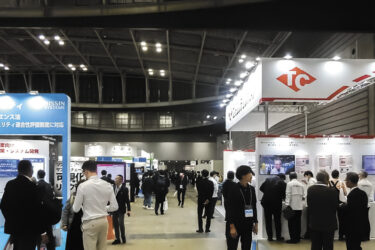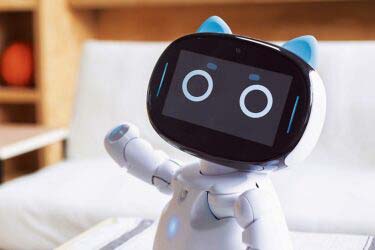2025.08.28 大手報道機関が米AI企業を相次ぎ提訴、記事の無断利用で著作権侵害
生成AI(人工知能)が急速に進化する動きが、報道機関を揺るがす事態に発展している。生成AIを活用した検索サービスを提供する米国のパープレキシティ(カリフォルニア州)が記事を無断で収集・利用したとして、朝日新聞社と日本経済新聞社が著作権侵害行為の差し止めと損害賠償を求める訴訟を26日、東京地裁に提起した。パープレキシティを巡っては読売新聞社も提訴しており、コンテンツ保護のあり方について議論を深めるきっかけとなりそうだ。
パープレキシティは、2022年創業の新興企業。朝日と日経の発表によると、パープレキシティは利用者から受けた質問に関連する情報をインターネット上で収集して生成AIに入力し、出力された回答を提供するサービスを運営している。朝日と日経のサーバーなどに収録された記事について、許諾を得ずに複製・保存し、遅くとも24年6月ごろから記事が含まれた回答を利用者の端末に繰り返し表示している。
記事の無断利用を防ぐため両社は自社サイトに、情報収集するクローラーを管理する「robots.txt」という技術的な措置を施し、記事の利用を拒否する意思表示をしているが、パープレキシティはこれを無視して利用を継続。無許諾で回答に使われたコンテンツには、日経が有料会員にのみ提供する記事や朝日が提携先に配信した記事が含まれているという。
そこで両社は、記事の複製・送信の差し止めや保存した文章の削除などを要求。合わせて、著作権侵害や不正競争行為で被った損害の一部として、各22億円を請求することにした。
「ただ乗り」を問題視
両社は、記者が膨大な時間と労力を費やして取材・執筆した記事について、対価を支払わずに「ただ乗り」するパープレキシティの行為を問題視。この事態を放置すれば、事実を正確に伝える使命を重視する報道機関全体の基盤が破壊され、ひいては民主主義の根幹を揺るがしかねないとして昨年夏から協議を続け、今回の共同提訴に踏み切った。
朝日広報部は発表したコメントの中で「当社のみならず日本新聞協会を通じて業界全体でも対応を求めてきた。改善がみられないまま無断利用が続く状況は看過できず今回、問題意識を共有する日本経済新聞社との共同提訴に至った」とした上で、「許諾を得ずに違法な利用を続ける事業者には、引き続き対応を求める」と述べた。日経広報室もコメントを発信し、その中で「共同提訴によって記事を許諾なしに利用していることを明確にし、野放図な著作権侵害に歯止めをかけたいと考えている。民主主義の根幹を支える健全な報道を守る意義を訴えていく」との認識を示した。
7日には、読売新聞東京本社、大阪本社、西部本社の3社がパープレキシティを相手取り、読売新聞オンライン上の記事の複製行為の差し止めと約21億6800万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こした。発表した読売新聞グループ本社の広報部は、公開したコメントの中で「多大な労力と費用をかけて取材をした成果である記事などの著作物が大量に取得・複製され、生成AIによるサービスに利用されていた事実は看過できず、提訴に至った」とした上で、「ただ乗りを許せば、取材に裏付けられた正確な報道に負の影響をもたらし、民主主義の基盤を揺るがしかねない」と強調。「訴訟を通じて、急速に普及する生成AIの規律や利活用のあり方を問いたい」との考えも示した。
急がれる制度の整備
日本新聞協会によると、AI事業者に対し、報道コンテンツを生成AIに利用する場合には許諾を得るよう繰り返し求めてきたが、改善がみられないままサービスは拡大の一途をたどっている。特にウェブ上の検索と連動してAIが回答を生成するサービスは、情報源となるコンテンツを無断利用し、記事と類似した回答の表示も多く、著作権侵害に該当する可能性が高いという。6月には、新聞協会が「生成AIにおける報道コンテンツの保護」に関する声明を発表。この中で、データ収集を行う事業者が技術的措置を施してコンテンツ保護の意思を示す権利者を尊重するよう要求。政府や国会に対しては、コンテンツの適正な保護に向けた制度整備を求めた。
生成AIと著作権の関係に関する懸念の解消に向けては、国も動き出している。文化庁がAIと著作権に関する考え方について整理したほか、24年4月には経済産業省と総務省がまとめた指針「AI事業者ガイドライン」が公開された。今年5月には、AIの開発促進とリスク対応の両立を目指す新法が成立。この中に、国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析と対策の検討を進め、その結果に基づいて必要な措置を講じる方針が盛り込まれた。ただ、AIと共存するための環境づくりは途上で、新聞協会は声明の中で、「報道コンテンツの保護は極めて心もとないと言わざるを得ない」と指摘した。
ユーザーがAIの回答に満足し参照元のウェブサイトを訪れない「ゼロクリックサーチ」の問題も、報道機関に影を落としている。報道の機能が低下すれば、国民の「知る権利」を阻害しかねない。それだけに官民挙げて、コンテンツの権利者を守る有効策を探る必要がありそうだ。