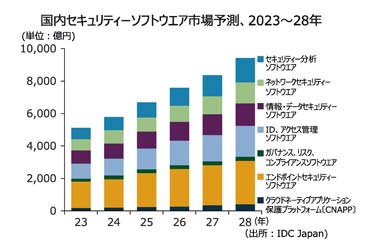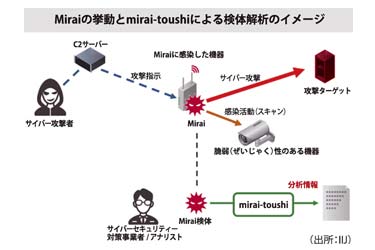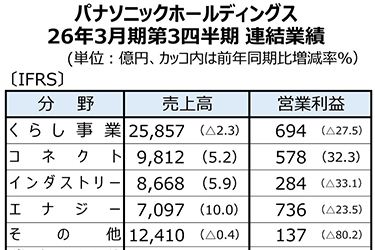2025.09.21 政府、サイバー脅威に対応する新戦略を年内策定へ 専門家会議が始動
サイバーセキュリティ推進専門家会議であいさつする平将明サイバー安全保障担当相(右隅)=東京都千代田区
政府は、年内をめどに新たな「サイバーセキュリティ戦略」を策定するため、専門家会議を立ち上げた。増大するサイバー攻撃の脅威に備える対応で、国が要となって官民一体でセキュリティー対策を推進する方向で議論を深めていく。国家を支える重要インフラなどを攻撃から守る「サイバー安全保障」も重視し、この分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させることを狙う。
政府は5月、先手を打ちサイバー攻撃の被害を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の関連法を成立させた。そうした動きを踏まえて19日、「サイバーセキュリティ推進専門家会議」の初会合を開催。会合に新戦略の策定に向けた議論のたたき台となる骨子を示し、意見を交わした。専門家会議は、東京大学大学院や一橋大学大学院の教授や弁護士らで構成。みずほフィナンシャルグループや三菱電機、KDDIなどの民間各社からも、関係者が参加した。
骨子では、サイバー空間を取り巻く現状認識などを示した上で、「深刻化するサイバー脅威に対する防止・抑止の実現」「幅広い主体による社会全体のサイバーセキュリティーとレジリエンスの向上」「サイバー対応能力を支える人材と技術に係るエコシステムの形成」を柱に施策を進めるという方向性を明示した。
具体的には1つ目の柱で、総合的な調整役「ナショナルサート」としてインシデントへの対処を高度化するなど、国が要となってサイバー脅威に対応する施策を推進。官民連携を促すエコシステムの実現やグローバルレベルでセキュリティーを強化するための国際連携の推進といった施策も盛り込んだ。2つ目の柱では、政府機関などが範となり、重要インフラ事業者や地方公共団体から中小企業まで含めた多様な主体に求められる対策を明確化する方針を示した。
3つ目の柱では、サイバー対応能力を支える人材や技術に注目。産官学を通じてセキュリティー人材を育成・確保することに加えて、国産を核に新たな技術・サービスを生み出すエコシステムを形成するという方針も盛り込んだ。先端技術への対応にも触れ、AIを活用したセキュリティーを強化する方針などを明記。量子コンピューターを用いても解読が難しい暗号技術「耐量子計算機暗号(PQC)」も取り上げた。
官民一体で対策を推進
平将明サイバー安全保障担当相は初会合の冒頭あいさつで、「サイバー空間を取り巻く切迫した情勢に対応するには、(関連法の)サイバー対処能力強化法に基づく取り組みを含め、国が対策の要となってわが国全体をけん引するとともに、官民一体で対策を推進していくことが不可欠」と強調。その上で、「中長期的に政府が取り組むべきサイバーセキュリティー政策の方向性を内外に示していきたい」と意欲を示した。
政府が戦略づくりを急ぐ背景には、国家を背景としたサイバー攻撃への懸念の高まりがある。さらにデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴い、攻撃が多様化・複雑化している状況で、サイバー対処能力の強化が喫緊の課題となっていた。こうした中で同日には、サイバー対処能力強化法の施行に関する有識者会議の初会合も開催した。有識者会議の検討を踏まえ、12月をめどに同法に基づく基本方針を策定することを目指す。