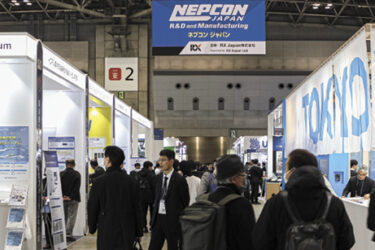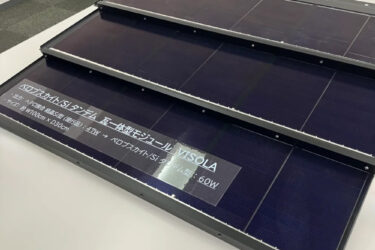2021.06.22 【この一冊】「男の子になりたかった女の子になりたかった女の子」松田青子 著(中央公論新社)
来週からリモートワークになると夫から告げられた女は、一歳半の幼児をベビーカーに乗せて家を出る。
「この家にこの人と閉じ込められる。考えただけで、喉がぎゅううと締めつけられ、実際に首を絞められているのかと錯覚した」。
コロナ禍で観光客が消えた古都とおぼしき街で、母娘はチェーンのホテルの一室を仮の根城によそ者としての日々を所在なくやり過ごす。LINEのメッセージは懇願から罵倒に変わり返信しないままたまり続ける。
一瞬たりとも目が離せない娘がようやく眠った。隣室の男子学生たちが深夜まで騒いでいる。母は力任せに壁をたたいて抗議する。壁の向こう、その先は誰も母娘を守ってくれずグーグルマップしか頼りになれないこの社会。初の女性副大統領の姿がテレビに映る。
連作短編集で語られるのは居場所を脅かされてさまようこの若い母のほか、向かいの部屋に住む同性の一人暮らしの孤高に淡い共感を覚えたり、きつい立ち仕事の疲れを癒やす入浴のひととき、突然「オレンジジュース」になった生理の血の鮮色に目を奪われたりする女性たち。
時に嫁入り前の娘を擬人化した、客に買われていくのを待つゼリー(洋菓子のあれだ)だったり、親しくなれないまま別れた、米高校留学時代のホームステイ先の少し年上のお姉さんが十数年後にふいによみがえったバースデーカードの電子音だったり―と設定はヘンテコでカラフルで自在。
表題作はメアリー・スチュアート・マスターソンやウィノナ・ライダーの映画が「ひとつのはじまり」になった女の子の話。
夢中になったのは、男の子みたいな短髪の容姿だったからだけではない。彼女たちが「今いる場所に居心地の悪さを覚えている」からであり、「自分が永遠の『部外者』であることを直感している」から。「女の子であること」から逃げ続ける女の子は、夫のDVから逃げる母娘の姿でもある。
どの作品の女性たちも、「女の子」の衣装をあてがわれた痛みや口惜しさ、歯がゆさに苦い舌打ちをし、乾いた嘆息を漏らす。羞恥の記憶を無効化し、男が語りたがる「物語」をズタズタに切り刻むため想像のはさみを振るう。
彼女たちが求めるのは、「連帯」と呼ぶには熱し過ぎず、さりげなく押し付けがましさのない、緩やかなつながり。何かあったらそんな存在が助けになり、彼女たちを少しだけ励ましてくれる。
「わたしたちは、会ったことはなくとも、つながっている」
中央公論新社。232ページ、1650円(税込み)。