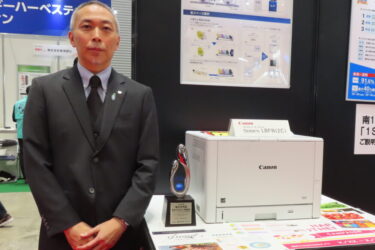2020.06.19 【冷蔵庫特集】自粛緩和で商戦活発化在宅で買い置き需要、大容量品に関心高まる
在宅の機会が増え、食材をおいしく長期保存できる大容量冷蔵庫への関心が高まる
冷蔵庫は夏商戦を迎え、これから本格的な盛り上がりに期待がかかる。今年は新型コロナウイルスの影響で外出が自粛となったことから、店頭への来店客数が減少、販売にも影響が出ていたが、自粛緩和となって以降は、商戦も活発化し始めたようだ。
在宅が増えたことで、今年は冷蔵庫の使用頻度は高まっており、特に買い置きの冷凍保存食品を収納する大容量冷蔵庫への関心が高まっている。買い替え需要喚起の好機が訪れている。
冷蔵庫は、毎年安定した需要が見込める商品だが、昨年から今年にかけては、消費税増税の駆け込み需要・その反動、新型コロナ影響と、試練に見舞われている。
ただ、基本的には堅調な需要があり、必需品であるだけに安定した買い替え需要は必ずある。
メーカー各社では冷凍・冷蔵性能の進化や省エネ・収納性(コンパクト・大容量の両立)など使い勝手、ガラスドア採用などデザイン性、IoT対応など総合的な商品進化に力を入れている。
こうした付加価値の高い商品戦略が、冷蔵庫提案において単価アップにも貢献、商戦活性化の期待を高める。
市場動向
冷蔵庫の需要は、このところ年間400万台程度の安定した需要があり、大きく伸びたり、落ち込んだりという振れ幅の少ない商品分野だ。
ただ昨年度、今年度と様々な要因で、振れ幅が大きくなったのは、冷蔵庫商戦において異例のことだった。
今後の商戦においては、進化した最新冷蔵庫のメリットをしっかり訴求することも含め、幅広い観点で活性化対策が問われることになってきそうだ。
冷蔵庫は基本的に買い替え需要が中心の安定した動きを示すものの、今期については、やや不透明な状況下にある。
こうした中、冷蔵庫の買い替え需要を顕在化させる商品的な切り口の一つは、大容量化と合わせ、設置面積に配慮したコンパクト性だろう。
大容量化については401リットル以上の大型冷蔵庫の構成比は着実に高まっており、501リットル以上へのシフトも進んでいる。
市場では501リットル以上の超大型冷蔵庫の構成比は、2割程度まで上がっている。10年前と比較すると501リットル以上の超大型冷蔵庫の出荷構成比は倍増。顕著に大容量化は進んでいるといえる。
こうした大容量化の背景には、共働き世帯の増加で、冷凍食品や作り置きなど収納する食材が格段に増えたことが影響している。
市場では、共働き世帯が年々増加しており、専業主婦世帯(約600万世帯)に比べ、共働き世帯は1200万世帯強と2倍の開きがある(18年/総務省)。
共働き世帯では忙しい合間に料理を作ったりするために、冷凍食品の買いだめや肉・魚・野菜など生鮮食品のまとめ買い・冷凍保存、作り置きの食材の長期保存で、使いたいときにこれらの食材で手軽に調理を済まそうとする場合が多い。
また、忙しい共働き世帯においては家事時間の短縮・効率化が求められるため、時短調理につながる冷凍食材などの活用には、関心が高い。
もともと市場では、新型コロナ前から消費税増税もあって、外食を控えて、内食・中食のいわゆる〝家食〟が増加傾向にあり、新型コロナによって、それが加速された。
家で調理する機会が増えたことから、冷蔵庫には収納性が求められ、より冷凍・冷蔵技術が進化した付加価値の高い大容量冷蔵庫の提案をしやすい環境になっている。
緊急事態宣言が解除され、感染拡大の第2波が懸念されるものの、自粛緩和へとフェーズが変わった中で、販売店頭への来店客数も次第に戻りつつあり、冷蔵庫商戦も活発化しつつある。
パナソニックによると、外出自粛の緩和以降、冷蔵庫販売は前年2桁の伸長ペースに回復したという。
自粛期間のマイナス分をカバーするチャンスが巡ってきており、最新モデルへの買い替え提案は夏商戦に向け重要となる。
各社、鮮度保持性能向上に力
商品戦略
冷蔵庫各社の商品戦略は、大容量化ニーズへの対応をはじめ、冷蔵・冷凍技術の進化など、鮮度保持性能の向上に力を入れる。
パナソニックでは最新の6WPXシリーズにおいて、業務用レベルの急速冷凍技術を盛り込み、生鮮食材の新鮮保存と解凍後のおいしさの両立に取り組んでいる。
同社のはやうま冷却・はやうま冷凍搭載IoT対応WPXシリーズのユーザーのログ分析によると、平日は弁当のあら熱取り(はやうま冷却)、休日は作り置きを急速冷凍(はやうま冷凍)するなど、機能をしっかり使い分けていたことが分かっている。
その上で、今年は在宅が増え、時短・かつおいしく、栄養バランスの良い料理へのニーズが高まっていることから、「冷凍調理」提案を強めていく。
業務用レベルの冷凍性能を持つ〝はやうま冷凍〟は、素早く冷凍することで食品の細胞破壊を抑え、うまみ成分を逃がさず、おいしさをキープした冷凍ができる。
この特性を生かし、肉、魚、さらには野菜(カット野菜)まで、おいしさを維持して冷凍保存することで、時短調理に生かす幅広いメニュー提案を強化している。
同社では昨年(3月)に〝はやうま冷凍/冷却〟を搭載した冷蔵庫を投入してから、冷蔵庫を従来の〝保存庫〟から、〝調理庫〟へと進化させ、冷蔵庫に調理アシスト機能を付加し、内食ニーズに応える商品戦略に取り組んだ。
今年2月に発売した6WPXシリーズは、はやうま冷却がさらに進化しており、アツアツご飯を入れた弁当も3分で冷却できるようにして、時短調理ニーズに応えている。
三菱電機も冷凍機能をさらに進化させ、新しい生活様式に対応した冷凍技術の提案を強化する。
肉や魚などの生鮮食品を生のまま長持ち(最長約10日間)させる「氷点下ストッカーD A,I.」、冷凍ながら解凍いらずで、すぐに調理できる「切れちゃう瞬冷凍A.Ⅰ.」(保存期間約3週間)、さらに長く(約1カ月)保存できる「冷凍室」と、多様な冷凍機能を搭載している。
約マイナス7度で凍らせる切れちゃう瞬冷凍A.I.は、冷凍した食材を解凍なしですぐに調理できる利便性をアピールする。
「置けるスマート大容量」MXシリーズでは、AI(人工知能)がユーザーの生活パターンを予測して自動制御する、切れちゃう瞬冷凍A.I.に進化。従来食品を入れるたびに必要だった設定が不要になり、使いやすくなった。
さらに、肉や魚に加えカット野菜も下ゆでせずに生のまま冷凍を可能とし、凍ったまま必要な分だけ簡単に手でほぐせ、調理時間の短縮に貢献する。
同社では野菜室が真ん中タイプのMX・MBシリーズ、冷凍庫が真ん中のWXシリーズを主力に、幅広いユーザーニーズに応えるラインアップで市場に臨む。
冷蔵庫各社では、こうした冷凍技術の進化のほか、鮮度保持性能の向上、大容量ながら真空断熱材採用によるコンパクト性の追求、省エネ性の向上、デザイン性の強化、IoT対応の加速など、様々な切り口で商品進化に力を入れている。
IoT対応も近年は加速しており、スマートフォンで冷蔵庫の設定(庫内温度など)や運転状況の確認、レシピ提案、役立ち情報の提供、ほかの家電機器との連携など、新しい使い方の提案も始まっている。