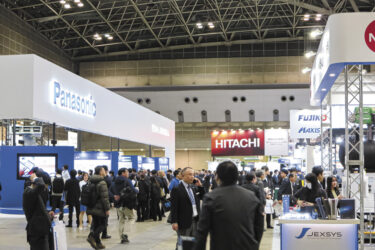2025.04.23 ソニー系のロボット玩具 「プログラミング教材」としても存在感 開発者の田中章愛氏に聞く
toioの生みの親、田中シニアマネジャー
小さな四角いキューブを動かすロボットトイ「toio(トイオ)」が、次世代玩具として注目を集めている。手掛けるのは、ソニーグループ傘下のゲーム子会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)で、2019年に発売。24年には、キューブと専用カードだけで遊べる「トイオ・プレイグランド」を用意した。この玩具をプログラミング教材として生かす狙いは何か。トイオの生みの親、toio事業推進室の田中章愛シニアマネジャーに商品に込めた思いや戦略を聞いた。... (つづく)