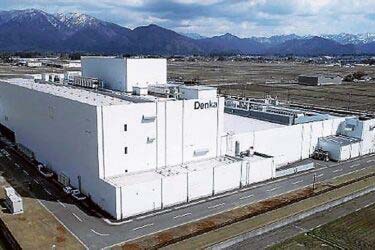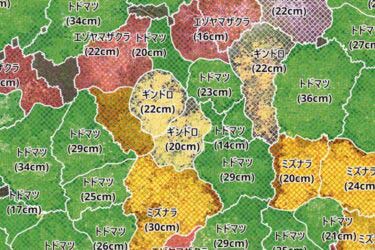2025.09.04 医療データを治療法や医薬品の開発へ 内閣府の検討会が活用策議論
内閣府の検討会であいさつする城内実科学技術担当相(左から2人目)=東京都千代田区
内閣府は、医療データを有効な治療法や医薬品などの開発につなげるため、検討会を立ち上げた。対象データの範囲や円滑なデータ活用に必要な情報連携基盤のあり方などをテーマに検討を重ね、12月にも中間的な取りまとめを行う。その上で、2026年夏をめどに議論を整理。必要な措置が法改正を要する場合には、27年通常国会への法案の提出を目指す。
今回設置したのは「医療等情報の利活用の推進に関する検討会」で、座長は東京大学名誉教授の森田朗氏が務める。構成員として、日本製薬工業協会や経団連、日本医師会、国立情報学研究所、国立がん研究センターなどの関係者が参加した。
内閣府によると、想定する医療データは、「電子カルテ」や個人が持つ健康情報や医療データを表す「PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)」など。研究者や企業が蓄積したビッグデータを分析できる環境を整え、治療法などの開発に役立てたい考えだ。
検討会で取り上げる論点の1つが医療データの収集方法で、一定の強制力やインセンティブ(動機付け)で医療機関や学界などから情報を集める展開を想定している。さらに、文書や画像などの形で集めた情報を研究開発で使いやすいようAI(人工知能)で構造化する取り組みにも焦点を当てる。
一方、医療データは機微性が高い情報で、特定の個人が識別され情報が漏えいした場合に権利侵害につながる。こうしたリスクを踏まえて、患者の権利・利益の保護や情報セキュリティーの確保といった論点も取り上げる。また、医療データを活用する際の費用負担のあり方についても探る。3日に開かれた初会合では、参加した有識者がさまざまな観点から議論し、多様な意見が挙がったという。
イノベーションの成果を国民に還元へ
城内実科学技術担当相は会合冒頭のあいさつで、「有効な治療法や医薬品、医療機器などを開発し、医療の質向上を図っていくためには、医療データの利活用を一層促進することが大事だ」とした上で、医療現場や国民・患者の十分な理解を得ながらデータ活用を促すバランスを重視する考えを強調。「医学、医療のイノベーションの成果を国民、患者にしっかりと還元できるよう率直な議論をしてほしい」とも述べた。
政府が6月に閣議決定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では、医療データの二次利用を制度的にさらに円滑化することを目的に、医療データの利活用に関する基本理念や制度的な枠組みなどを含むグランドデザイン(全体像)を描く方針を示していた。