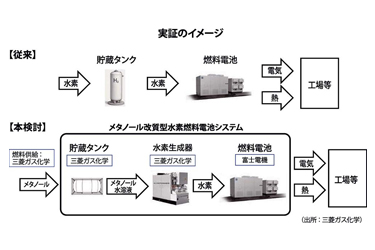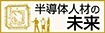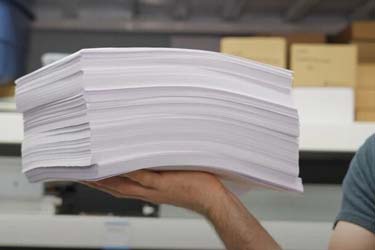2025.11.18 NTT、光量子コンピューターの開発で東大発スタートアップと連携 100万量子ビット実現へ
連携協定を締結したNTTの島田社長(左)とOptQCの高瀬寛CEO=18日、東京都武蔵野市
NTTと東京大学発スタートアップのOptQC(東京都豊島区)は18日、光の特性を活用する次世代計算機「光量子コンピューター」の実用化に向けた連携協定を結んだと発表した。両社の技術を持ち寄り、量子コンピューターの性能を表す「量子ビット」の数で2030年までに世界トップレベルとなる100万個の実現を目指す。消費電力が低く常温・常圧で動作可能な光方式の強みを生かし、大規模で複雑な社会課題の解決に役立つ光量子コンピューターの社会実装に向けた道筋をつける。
OptQCは、東大での25年にわたる光量子コンピューターの基礎研究を土台に設立されたスタートアップ。NTTの島田明社長は同日開いた記者会見で、自社で培った光通信技術にOptQCが持つ光量子コンピューターの開発技術を融合し、「スケーラブルで信頼性の高い光量子コンピューターの実現を目指す」と強調。「光方式で量子ビット数を拡張することで、従来のコンピューターでは生み出すことのできない価値を創造したい」とも力を込めた。
量子力学の原理を利用した量子コンピューターは、従来のコンピューターでは膨大な計算時間を要する複雑な課題の解決に有効とされる計算機。NTTは、光方式の量子コンピューターで27年に1万個の量子ビットを達成する目標を表明。次に100万個を狙い、社会課題の解決に貢献するアプリケーションの開発を目指す方針も示した。空気中の窒素から肥料を低エネルギーで生成するための計算など、地球規模の問題を解決するために必要な計算を数日で終えることが可能になるレベルという。
量子コンピューターを巡っては、国内外の企業や研究機関が多様な方式を提案し、熾烈な開発競争を繰り広げている。超電導やイオントラップ、中性原子といった方式は、巨大な冷却装置や大規模な制御装置が必要となるため、多くの電力を消費する。光方式はこうした装置を不要にできるため、エネルギー効率の面で優位に立っている。
島田社長はこうした強みにも触れた上で、「約60年にわたって光技術を研究開発し、実用化してきた。その中のいくつかの技術が量子分野に応用が可能ということがわかってきた」と力説。24年には光増幅技術を活用し、従来の1000倍以上高速に量子を生成できる量子光源の実現に成功したという。こうした実績を土台にOptQCと連携し、光量子コンピューターの実用化に向けた取り組みに弾みをつけたい考えだ。