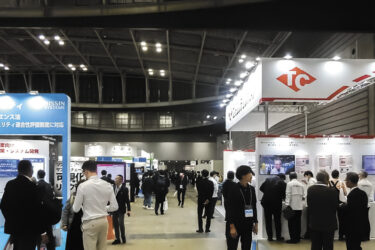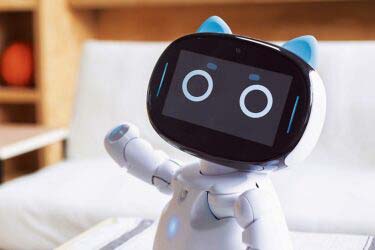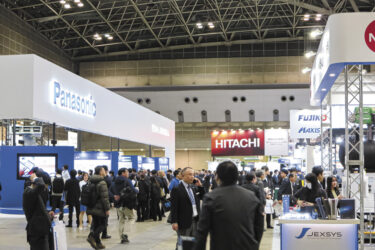2025.09.22 NTTドコモビジネス、AIエージェント時代の業務変革を後押し 最新戦略に迫る
取材に応じるNTTドコモビジネスの荒川大輝ジェネレーティブAIタスクフォース長=東京都千代田区
NTTドコモビジネス(旧NTTコミュニケーションズ)は今夏、20種類の業務を自律的にこなす「AI(人工知能)エージェント」を用いたソリューションの提供に乗り出した。複数のAIエージェントに業界固有の知識やルールなどのデータを掛け合わせ、文書作成やデータ分析などの業務を自動化できるようにした。2026年を目標にAIエージェントを200種類に増やし、人間とAIが協働する社会づくりを支援したい考えだ。同社ビジネスソリューション本部スマートワールドビジネス部ジェネレーティブAIタスクフォース長の荒川大輝氏を取材し、今後のAI戦略について聞いた。
――米オープンAIの「Chat(チャット)GPT」の登場で、AIが一気に身近な存在となりました。AIの進化をどう見ていますか。
荒川氏 ありとあらゆるデータを使いながら、業務やユーザーエクスペリエンス(ユーザー体験)を革新的に変えられるようになった。まさに「AIを使う時代」から「AIを使う前提で業務を変革する時代」へ変化しつつある。
――既存事業にAIをどう生かしていますか。
荒川氏 これまで当社は、CX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)とEX(エンプロイーエクスペリエンス=従業員体験)、サイバー攻撃の被害を最小化し事業の継続性を高めるCRX(サイバーレジリエンストランスフォーメーション)という3つの領域に対して、さまざまなソリューションを提供してきた。例えば、CXの領域では、顧客接点を担うコンタクトセンターの支援などに取り組んでいる。さらに、ICT(情報通信技術)を駆使したスマートな社会「Smart World(スマートワールド)」の実現につながる多彩なソリューションも提供している。1つが、未来の街づくりや製造業の生産性向上を支援するソリューションだ。こうした既存の事業にAIを取り入れことで、顧客の変革をサポートする体制をより高度化していきたい。
多業界にAIが入り込む世界を
――AIエージェントが企業に与える影響は。
荒川氏 大量のデータを基に事前学習した「LLM(大規模言語モデル)」や外部情報を参照して回答を生成する「RAG(検索拡張生成)」を活用する機会が広がっているが、AIを能動的に活用する取り組みはまだまだ途上にある。「気づいたらAIを使っていた」という世界を作り出す必要がある。そうした中で注目を集めているツールが、従業員に代わって自律的に考え実行してくれるAIエージェントだ。例えば、出張を計画する社員に寄り添い、手続きが完了するまでサポートしてくれる。そんなAIエージェントがさまざまな業界にどんどん入り込むと、今までと違う業務の形が生まれてくる。AIエージェントの有効な活用事例を積み上げていきたい。
――20種類の提供方法と事業目標は。
荒川氏 1種類のAIエージェントで1業界をカバーするのではなく、20種類でさまざまな業界の個別ニーズに対応していく。例えば、製造業向けに「知財文書作成エージェント」を用意し、特許申請に必要な書類作成までの一連の業務を支援する。金融業界のセールス業務を高度化するニーズにも応え、複数のAIエージェントと人が協働しながら顧客への提案書を効率よく作成できるようする。当面のターゲットは、専門性が高い業務が多い金融や製造、公共などだ。来年には、種類を10倍に拡大する計画だ。AIエージェントをカスタマイズすることで、全ての業界をカバーできると考えている。
――AI事業で武器となる強みは。
荒川氏 1つは、クラウド上の保存データやエッジ側で処理されるデータなど、あらゆる情報を取りそろえて展開できる点だ。AIエージェントと人間が協働する社会を見据え、エージェントの実用性を高める取り組みに徹底的にこだわっていきたい。AI利用時に安全性を高める技術を保有していることも強み。AIの入出力を監視し、必要に応じてブロックするガードレール技術「chakoshi(チャコシ)」などが一例だ。
実用性とリスク対応が普及の鍵に
――AIの普及に向けた課題と企業に問われる能力は。
荒川氏 業務で使えるよう実用性を高めることが課題の1つ。生成AIが誤った回答を生み出す「ハルシネーション(幻覚)」というリスクを理解し、人間がしっかりと生成した回答を見定める必要がある。また、AIがより生かされるビジネスプロセスやデータマネジメントも重要となる。そうした課題を解決していけば、AIエージェントと上手く協働するスタイルが当たり前になるだろう。
人材というリソース(資源)のかけ方と配置が確実に変わるだろう。AIエージェントの導入に伴い浮いた人的資源を注力する成長分野に投下するといった取り組みが想定される。つまり、AIエージェントの活用は、コストと品質の両面から業務のあり方を根本から見直すきっかけとなる。企業の経営者には、AIの活用を前提に組織や事業をベストな方向へと導く判断能力が、より試されることになる。