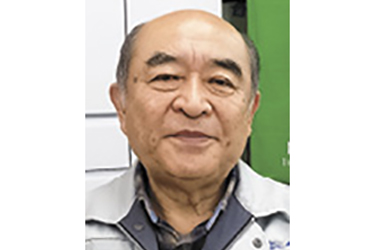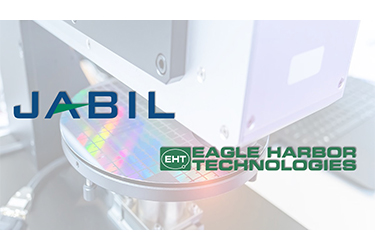2025.09.30 【電波新聞75周年特集】 電波新聞社創立75周年に寄せて 「伝統とは 革新とは」狂言師 野村萬斎
権威だけでは形骸化する
—700年近く時を重ねてきた能、狂言の歴史と現代をどう見ていますか。以前、著書で「伝統を権威化してはならない」と書かれていましたが。
コロナ禍を経て時代が一気に変わった感じがしますね。ライフスタイルの変化がわれわれには転換期になると思うのです。幕府や大名に抱えられていたのが明治維新に自由経済に投げ込まれたことも大きな転換期だと思います。
その頃は教養としての能文化があったので、かつての武家や貴族が手厚く守ってくれた。欧米化の波もあった。戦後は謡や舞を教えることで生計を立てた。それこそ企業や官公庁にも謡曲部というのがあったと思います。今はそういうコミュニティーがないのかな。伝統芸能以上にライフスタイルが変わってしまった。ライフスタイルが変わると電化製品と同じでそれに合わせていかないといけない。そうなると、権威を言っても過去の名声になってしまう。もちろんわれわれは伝統的なことをやっているから、一種の保守でなければいけない。型を、伝統を崩さないための一つの規範として守るべき人もいるわけで。宗家制度のように非常に厳格なところもある。
ただ時代とともにあらねば続かないというのが、僕の「権威だけでは形骸化してしまう」という思いなのです。
—「型がなければ型なし」と言いますが、口伝であれ書物であれ、型を伝えることが必要でしょうか。
電機関係や製造業の方々同様、芸能を伝えるわれわれも職人気質なところがあると思います。職人に何を本質的に求めるか。まずは技術ですよね。加えて技術を何に生かすか。目標や目的意識がないと成立しないでしょう。
僕らは新しいものを常に作り続けているわけではなくて。古典を演じることは、どちらかといえばリクリエーション、再創造の世界なんです。
よって重要なのはいかに「素材としての自分たちが新しいか」ということ。役者自身は今日生きている素材ですから、そこが製品というより料理に近いと思います。古典というレシピは決まっている。素材は生きのいい魚か、熟しているのか。年を取れば熟していると言えるし、若ければ生きの良さがいいのかもしれない。中間だったら心技体の充実感があるか。
見る側も今日の方なので、再創造するというのは今日的な意味というか、今を映す鏡でありたいと僕は思っています。それが伝統芸能の宿命というか、そうあるべきだと。
家電、エレクトロニクスだと今便利なモノとなるのでしょうが。面白いですね、対比して考えると。業界に特化した新聞社の取材を受けると、とたんに自分を照らし出すわけで。「己は何ぞや」と電気製品と伝統芸は何が違うのかと考える。生産ラインとしての仕組みは同じかもしれない。それぞれ役割分担があって。われわれは日進月歩が難しい点、やはり料理に近い。本質的に何を追い求めるべきか、その時、その時に考える必要があります。
役者として自己をフレッシュに魅力的に見せられるかも重要ですが、自分だけ魅力的でいいかというとそうではない。チームプレーですから。舞台の質を上げるには皆がうまくなきゃいけないし、みんなが機能しないといけない。
私たち一門には90歳を超えた父(野村万作さん)もいれば、25歳の長男、裕基もいるし、さまざまな年代、個性があり得意、不得意もある。いい舞台を作るためにチームワークをすごく考えます。
新作を作った時は、能も狂言もごちゃまぜで。能狂言「鬼滅の刃」は能・狂言の総力戦で取り組みました。
近くて違う世界を知る
—狂言に立脚しながら映画やドラマ、現代劇とさまざまなジャンルに関わることで何が見えてきましたか。
現代を知るために、他の世界を知る、近くて違う世界を知ることが必要ですよ。能舞台の上だけでは、井の中の蛙(かわず)となってしまう。逆に能楽堂に入るお客さんも勇気が要るのでは? 時には一種の閉じた世界、井戸から出ていって世界は広いなと知らなければ。
—万作先生は早くからさまざまなジャンルとコラボレーションをしてきました。
一種の伝統というべきかな。曽祖父の初世萬斎が加賀前田藩のお抱えから江戸に出てきたことも、ある種の冒険だったと思いますよ。そこから江戸に根を下ろすためにはどうしたらよいかと。地方の狂言師が中央に出てくる、まずそこに進取の気性を感じます。
—あらためて伝統とは、革新とは。
目的は何か、ということになるのでしょうか。94歳で現役の父を見ているとまさにミラクルな状況で、解脱の境地というか意識や体力もわれわれとは違う次元に到達していて、もう型を感じさせない自然体になるわけです。人間がそのままそこに存在することの面白さを体現していると。狙ってできるものではないと思います。
本質にたどり着くことをゴールとするならば、父を見ていると究極の芸は伝統も革新も最終的には関係ないと思ってしまいますが、極めて特殊な例なんでしょうね。
僕らは古典のレパートリーだけだと再生芸術、つまり繰り返しているだけだと言われることがあります。だから時々新作を作る。新しい、今までの概念を超えるものを生み出してみたり、世界を大きくはみ出してみたりする。僕は確信犯的にやっているつもりです。
能・狂言が本質的に崩れるようなことをするつもりはまったくなくて。あくまで能・狂言の範囲で新作をやりますね。一方で能・狂言では絶対にやらないこともやってみたい。例えば能・狂言には出てこない大悪党を演じてみたいのなら現代劇に出る。本業と分ける。でも、演じるということではつながっている。狂言師も俳優も違いはあれど、同じところもあるわけです。
—芸術の世界に終わりはないですね。
正解がない。製品の場合だったら売れればひとつ正解ということになるかもしれないけど。芸術は果てしない。もちろん製品もそうでしょうが。
伝統芸能の厳しいところは、前の価値観との相克というか。新製品を手放しに喜んでもらえるとは限らない。若い観客層には面白がってもらえても、古い価値観の人に認めてもらえない場合もある。
演者はアップデートしてきたから能・狂言は700年続いてきたけれど、アップデートできない人もいるわけです。先代などと比べられるのは伝統芸能の宿命ではありますが。時代の変化に対応してアップデートを続けるのは本当に大変です。
今を生きるわれわれが、今を生きる皆さんとライブで見せる瞬間を共有することが舞台芸術、ライブパフォーミングアーツの醍醐味(だいごみ)があるとすれば、それを信じてやるしかないな、と。
私は私の時代感の中で、一つの自分の境地に至れることがあったらいいなと。もがき続けるしかない。深いし、楽ではありません。
能・狂言を含め、劇場ではコロナ禍以降、平日夜に観劇する方がずいぶん減ってしまい、土・日曜にお客さんが集中する観劇習慣の傾向があります。これもライフスタイルの変化です。
日刊新聞が週刊新聞へと変わるのと同じ気がします。ライフスタイルが変化しても、伝えるべき時間と場所できちんと伝えることを信念として持ちたいですよね。変化に対応することは当然で、その中で何を伝えるか。
僕は若い時に海外留学をして、その時、自らのアイデンティティーとは、本質は何か、じっくり考えたことが今でも活動の根幹になっています。本質は何かということを僕は考え続けたいし、メディアは伝えてほしいと思っています。
野村萬斎(のむら・まんさい) 1966年生まれ、東京都出身。祖父・故六世野村万蔵及び父・野村万作に師事。重要無形文化財総合指定者。3歳で初舞台。東京芸術大学音楽学部卒業。「狂言ござる乃座」主宰。国内外で多数の狂言・能公演に参加、普及に貢献する一方、現代劇や映画・テレビドラマの主演、舞台をはじめ、古典の技法を駆使した作品の演出など幅広く活躍している。
「狂言ござる乃座」71st 10月22日午後7時開演、東京都文京区の宝生能楽堂。同26日午後2時開演、東京都渋谷区の国立能楽堂。狂言「合柿」、狂言による「彦市ばなし」ほか。20回記念「狂言ござる乃座」京都公演は、同12日午後2時開演、京都市左京区の京都観世会館。狂言「金岡」「鬼瓦」「鳴子」など。問い合わせは、万作の会=03(5981)9778。