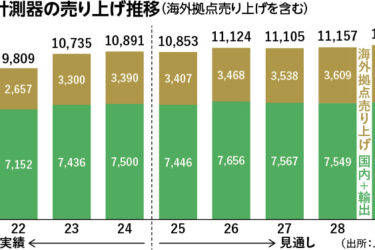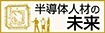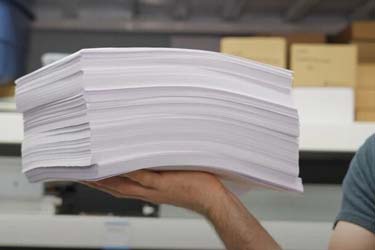2025.09.30 【電波新聞75周年特集】75年 これまでとこれから 電機業界
電機各社はデジタルやAIでさまざまな業界の中心となり成長を目指していく(写真は電機業界の共創を目指すCEATEC)
モノづくり技術と融合
デジタル技術利活用がカギ
電機業界はいま、新たな成長に向けて動き出している。日本の電機各社が戦後の成長を下支えしてきたことは間違いないが、この40年はさまざまな市場環境の変化にもまれながら自社の立ち位置の見極めをしているのが実情だ。現在の社会環境を見ると、全てがネットワークでつながり、クラウドやAI(人工知能)などデジタル技術の利活用が企業の成長の鍵を握る。そのデジタル技術の中核を担うのが電機業界でもある。これからも日本経済の成長を技術で支える重要な業界としてリードしていくことが求められる。
日本は戦後の高度成長により世界有数の経済大国にまで上り詰めた。トランジスタやテレビ、録画機、カメラなど、世界を席巻する技術と製品開発はいまでも日本の技術力を語る上で欠かせない。
その間、欧米との貿易摩擦や規制など逆境にさらされながらも技術を磨き、良い製品を投入してきた。
技術でリードも市場で負ける
1980年代以降、電機業界は大きな転換期を迎え、冬の時代に突入した。技術力とモノづくりを強みに成長してきた日本の電機各社にとって試練が続いた。例えばテレビや携帯電話、パソコンなど、日系電機各社の技術力が世界をリードしていたにもかかわらず市場競争では負けてしまった。
〝昭和の時代〟に世界で活躍した日本は、80年以降の〝平成の時代〟、勝てなくなった。技術力だけでは市場で勝てない時代になり、マーケティング施策が勝敗を分ける時代に突入した。
90年代以降は合従連衡が本格化し事業再編が続いた。半導体やディスプレー関連は、各社が個別に開発していてはグローバル企業に勝てないことから、日の丸連合として事業統合を開始。2000年以降、電機各社自身の再編が一気に加速した。事業統合や売却なども進み、10年代になると、海外企業を巻き込んだ事業構造の転換が進んできた。
08年のリーマンショックをきっかけに日立製作所が過去最大の赤字に転落。11年のアナログ放送停波はテレビを展開していた各社にとって大きな転換期となった。テレビで世界を取りに行っていたパナソニックやシャープは業績が悪化。特にシャープは存続危機にまで陥った。
比較的優等生だったソニーはテレビ事業など主要エレクトロニクス事業の苦戦が続いた。NECは構造改革の成果が思うように出ないまま歳月が過ぎた。さらに、東芝の不正会計問題が発生。電機業界自体の存在が改めて問われるようになった。
各社は再生を目指して事業売却や事業統合などを進め、日本企業という概念すら変わるようになってきた。自力での再生が難しかったシャープは台湾の鴻海精密工業の傘下に入って再生の道を選択。東芝は主力だった白物家電とテレビの事業をそれぞれ中国企業に譲渡した。
その後も総合電機と呼ばれる各社は再編を続け、20年代に入ってからの各社の事業ポートフォリオはかつての姿から大きく変わったといっても過言ではない。多くの電機メーカーが主軸に置いていた家電事業は、主力事業から外れたところが多い。特にテレビなどのAV機器から撤退した企業が多く、白物家電を見ても全方位で製品群をそろえているところは少ない。
総合家電メーカーと呼べる企業はパナソニックのみで、鴻海傘下のシャープがテレビも含め白物家電の開発に力を入れている。日立製作所では白物家電が中心となり、三菱電機は製品を絞り込んだ。
東芝は家電事業を中国メーカーに売却。ソニーはAV機器の開発製造販売を進めるものの、ゲーム、音楽、映画などのエンターテインメントを軸にしたエレクトロニクスという枠組みで事業展開を図る。富士通はソフトサービスの企業としての成長を目指そうとしている。
ポートフォリオ改革まだ続く
電機各社が30~40年にわたり進めてきた事業ポートフォリオ改革はまだ終わりを迎えていない。
電機各社が進めているのは、BtoB事業の一層の強化だ。各社は、製造業としてこれまで培ってきたモノづくりの知見とデジタル技術の融合を推し進め、日本が世界を席巻してきたモノづくり力にデジタル技術を掛け合わせて化学反応を起こす。
その中で各社が積極的に進めているのが、クラウドやAIといった最新のデジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みだ。特に生成AIを業務に適用していく動きが進み、事務作業などオフィス関連業務で生成AIを活用することは当たり前になってきた。
生成AIを正しく活用できるかがこれからの成長の鍵を握るという声も出ている。この1~2年の動きを見てもAIを核にしたデジタル事業は成長しているところが大半だ。電機各社が顧客先としているさまざまな業界の企業のデジタル化も進む。工場をはじめとした現場へのAIの適用も始まりつつあり、この先実用段階に入ってくるだろう。
世界的なAIの進展は関連産業にも恩恵をもたらし、半導体産業やデータセンター関連事業への投資も拡大している。
同時に、脱炭素化(カーボンニュートラル)への取り組みをさらに進めることも必要だ。この一年でもSDGs(持続可能な開発目標)の実現に向けた実践を始める企業が増え、さまざまなICT(情報通信技術)を活用した事例も出てきた。
これからは環境を意識した経営もさらに重要になるだろう。この一年、サステナビリティー(持続可能な)経営を掲げ、さまざまな施策を公表した企業も多かった。サステナビリティーを前面に出した取り組みが一層進むとみられる。
いま、電機各社は30年を見据えた経営施策を掲げている。少子高齢化、労働人口の減少への対応が求められ、デジタル技術を使った効率化や価値創造が欠かせないものになるだろう。